Blog インタビュー, ニュースなど
Interview Project 01 – 武田 光 (Cidernaut Owner)
Green Neghbors Hard Cider の及川 貴史と、ブランディングを手がける佐々木 新がホストとなり、毎回サイダーに関わるゲストを迎えて、日本における黎明期とも言える「サイダーカルチャーの現在地と未来」を探るインタビュー・プロジェクト。第一弾は、東京 渋谷/神泉のサイダーバー『Cidernaut』の武田 光さんを迎え、サイダーにまつわる幅広いお話をお聞きしました。
T : 武田 光 (Cidernaut Owner)
O : 及川 貴史 (サイダーメイカー/Green Neighbors Hard Cider)
S : 佐々木 新 (ブランドディレクター/HITSFAMILY)
日本サイダーカルチャーの間口となる『Cidernaut』

S : 武田さんがサイダーに出会ったのは、留学先であるイギリスだったとお聞きしましたが、オーナーとして経営されている『Cidernaut』では、イギリス産のものが多いのでしょうか?
T :『Cidernaut』を立ち上げる当初は、イギリスのものを中心に考えていたのですが、まず樽があまり日本に入ってきていないのと、サイダー自体が日本であまり知られていない状況だったので、サイダーの間口として世界中のものを取り扱うことにしました。そもそも、お酒は嗜好品なので、さまざまな味があり、好みもそれぞれ異なります。原料となるりんごの作り方でも異なりますし、産地によって全然味が変わってくるのが面白い。そうした様々な楽しみ方を提供することが、日本のサイダーカルチャーにとっても良いだろうと考えました。
S :『Cidernaut』というネーミングはそのような想いに関係があるのですか?
T : 宇宙飛行士の訓練をした人をアストロノートと呼びますが、「naut」は接尾語で”探索者”や”探求者”という意味なので、サイダーを探求する人、あるいは普及する人という意味が込められています。アストロノートは惑星を探究しますが、僕たちの場合はりんごなので、ロゴには宇宙飛行士とりんごがモティーフとして描かれています。

O : イギリスにはどのぐらい住んでいたのでしょうか?
T : IT関係の仕事を辞めてから、イギリスに留学しました。期間は、2007年から2014年の間、約6年強くらいですね。ちょうど僕が行った時は、コンサバティブという保守系が政権をとり、EU や歴史的にイギリスと関わりのあった国(一部の特定の国) 以外の人にとってはそれまでよりも色々と制限が増してきた時期でした。
O : サイダーとはどのように出会ったのですか?
T : よくよく考えてみると、どのようにしてサイダーを知ったのか全く覚えてないですね。恐らくパブでサイダーがあり、「これ何?」と訊いたのかもしれません。でも最初英語なんてほとんどしゃべれなかったですし、、、英語の先生が教えてくれたのでしょうか。うーん、全く覚えていないです。でもイギリスに着いて大分早い段階で飲んでいました。本能で見つけたのかもしれません 笑。
O : イギリスではサイダーを日常的に飲んでいたのでしょうか? また記憶に残っている美味しかったサイダーはありますか?
T : 僕は基本的にロンドンに住んでいたのですが、出かければパブで、家では近所のオフライセンスショップ(日本でいう小さいコンビニ)でビールと同じように売っていたので毎日のように飲んでいました。1年程ケント州に住む機会があり、あるパブの店内にタンクがあってサイダーを造っていたんです。そこで飲んだおそらく濾過もしていない白濁したサイダーは、今まで飲んだことのあるコマーシャルブランドのサイダーと比べものにならないくらい美味しいものでした。
O : そのパブで出会ったサイダーに衝撃を受けたんですね。
T : 本当に衝撃でした。今まで飲んだものと全然違いましたね。2種類あったのですが、1つは普通のサイダーで、もう1つはシナモンが入っていて、イギリスのクラフトではこんなことをやってしまうのだと驚きました。今考えると実は非常にレアですが、、、。

O : サイダーがきっかけで日本に戻って起業をしようと思ったのですか?
T : イギリスには6年間居たので、やれることはやり切った感がありました。それにビザの問題など、向こうに居続けるには就職しなければならないという事情もあった。ちょうどその頃、ある日本の会社から、帰国して仕事をしてほしい、というようなことも言われていたので戻ってきました。日本でまだ普及していないサイダーはビジネスチャンスだと思って起業も考えましたが、パブの運営などの知識は全くなくて、帰国後すぐ立ち上げるということはしませんでした。本格的に動き出したのは、それからしばらくして、イギリスで出会った方が日本のパブで働いていることを知ってからです。
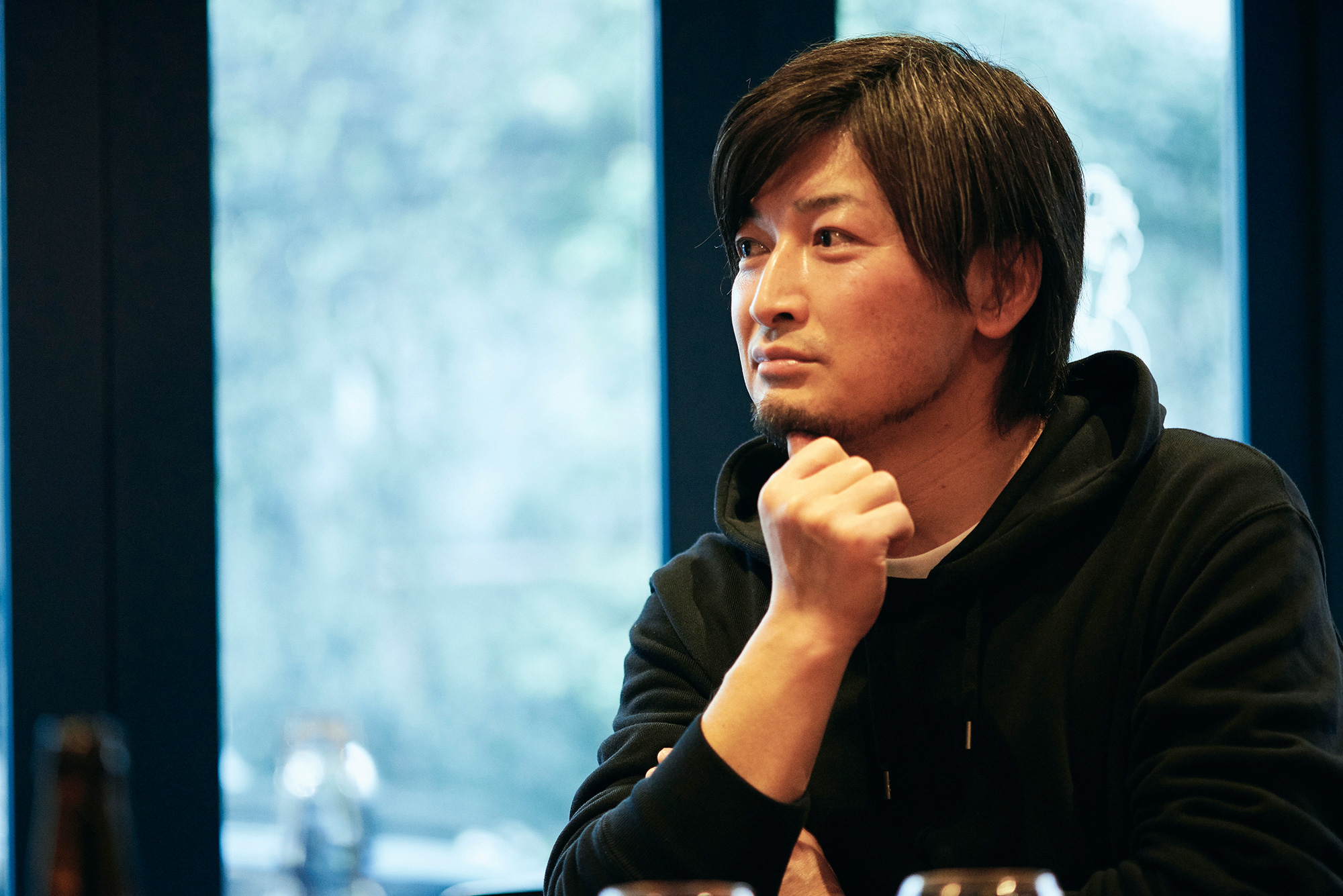
O : サイダーのパブをやろうと思った最大の理由は何ですか?
T : マーケットがニッチでリスクも大きいですが、やはりサイダーが好きだからですね。そもそも、日本だとあまり飲めないし飲み比べもできないから、そういったニーズを満たすお店にしたいと思い、『Cidernaut』を立ち上げました。
サイダーの背景に流れる
コミュニティやカルチャーも面白い

T : 及川さんは以前、焼き鳥屋やクラフトビール専門店『HOPPERS』をやられていましたが、どうしてハードサイダーを造ろうと思ったのですか?
O : いくつか理由はあるのですが、『HOPPERS』を立ち上げてしばらくしてから、扱うビールがどんどんフルーティで香りや苦味があるものに嗜好が寄っていったことが挙げられます。もうホップではなくて果汁でも良いのではないかなと 笑。そう思っていた時にハードサイダーを初めて飲みました。缶や瓶ではなくて、自分で注いでみたい欲求があったので樽で注文して、いよいよ自分でサービングしたらビールでなくてもいけるなと思ったのです。
T : ビール酵母や麦汁を使っているサイダーもありますし、クラフトという点でも世界観が近いですよね。
O : 『HOPPERS』に来てくださるお客さんの中にもフルーティーなビールは好きだけど苦いのは苦手というような人も一定数いたので、同じような世界観で提供できるものがあればと思い意識的にハードサイダーを増やしていきました。そこから缶とか瓶で常時20種類ぐらいお店に置くようになったのですが、認知度の低さのせいか、なかなか伝わらないこともありました。
T : その試み自体が結構前の話ですよね?
O : 僕が活動している岩手県はりんごがとても身近な果物なので、特別感がないということも大きいかもしれません。「美味しいから飲んでみてください」と言ってもなかなか受け入れてもらえず、だんだん自分で造ってしまった方が伝わりやすいかもしれないと思うようになりました。それにお店でサービングしてお客さんに提供していると、自分の職人気質な部分が出てきたということもあります。最初はサーブするだけで満足していたのですが、どんどん表現したくなって、自分でも気付かないうちにハードサイダー造りの道へ一歩一歩近づいていった感覚があります。そう思っていた時に、偶然、『くらしすた不動産』の星さんと出会いました。最初は「紫波町でブルワリーやってみませんか?」という話だったのですが、どうせ紫波でやるなら特産のりんごを使ったらどうだろうかと思って、実際にお店でハードサイダーを飲んでもらったのです。そういった偶然の出会いも含めて複数の要因の蓄積がハードサイダー造りをするきっかけになっていきました。



T : ブランディングする立場として佐々木さんはハードサイダーに最初どのような印象を受けました?
S : 最初にこのお仕事の相談を受けた時は、りんごのお酒というと甘いシードルのイメージが強かったです。だから、ハードサイダーとシードルの違いを知るところからスタートしました。ハードサイダーが美味しいと感じ始めたのは、及川さんが、『OK,ADAM』さん、『遠野醸造』さんと一緒に造った「D.A.V.」や『紫波サイダリー』さんのハードサイダーを飲み始めた頃でしょうか。それからより興味を持っていくのですが、個人的に一番面白いと感じたのは、ハードサイダーの背景に流れているコミュニティやカルチャーです。クラフトビールのブルワリーに火がついた時、新しい創造性に若い人が引き寄せられていきましたが、あの力に近いものがハードサイダーカルチャーにはあるように思います。味はもちろんのことですが、カルチャーやコミュニテイのあり方にも惹かれる人は多いのではないでしょうか。
ただ飲みにいくだけでは
お店に行く強い動機にはならない
誰かに会いたいという気持ちを尊重する

S : 東京の奥渋と言われる場所に『Cidernaut』を構えた理由は何ですか?
T : ここは渋谷から近いですが、少し外れていて落ち着いたエリアです。感度が高い人や外国の方もたくさん住んでいるので、新しいものが受け入れられやすく、かつ、発信しやすい場所だと考えてこの奥渋を選びました。ここなら、小さいながらも無理なく感度を保って発信できるのではないかなと思ったのです。
S :『Green Neighbors Hard Cider』は岩手県紫波町でサイダリーとして発信していくわけですが、武田さんから見て東北にはどのような印象を持っていますか?
T : 以前、及川さんと一緒に東北のブルワリーやサイダリーを周って、東北の熱を感じました。ただ、発信があまり上手ではなく、地域のまとまりがない印象もあります。何か東北のサイダーショーみたいなものがあるといいですよね。そうすると自然にお互いの顔も知って、地域としてまとまりが出てくるのかもしれません。

S : 今はサイダーにとって黎明期だと思うので、『Green Neighbors Hard Cider』は全国のサイダリーやブルワリー、生産者さん等とネットワークを作って一緒に盛り上げていきたいと思っています。また、及川さんの前職である『HOPPERS』では、造り手、お客さんそれぞれに関わりを持っていたので、そのエッセンスを残して、『Green Neighbors Hard Cider』のサイダリーに来てもらえれば、自分たちだけのものではなくあらゆるサイダーが飲めるようにできたらと話しています。造り手同士が敵対するのではなく、一緒にサイダーを広めていくような形にできたら、このカルチャー全般にとっても理想的ですよね。
T : その形が最高ですよね!よほどの老舗でもない限り、周りと協力していかないと絶対にやっていけないと思いますし。それに少し話がそれますが、コロナの影響で今まで以上に出かける動機付けとして‘人に会いにいく’という付加価値の重要さがさらに強くなってくると思います。地域や人と人のハブになるということを当店もミッションの一つとして掲げていますが、人と人が繋がる場所としてつくっていくのは理想的ですよね。

O : パブもブルワリーも、ただ飲みにいくだけではお店に行く強い動機にはならなくて、今は、誰かに会いに行くという理由でお店に行く感覚が強いですよね。そうして会いにきてくれた人たちに、僕たちもいろんなサイダーがあることを知ってもらいたいから、サイダリー内にタップルームを作って、自社だけでなく、さまざまなサイダーを飲んでみてほしいと思っています。
T : 新しいですね。
S : おそらくあらゆる状況がそうさせているのかもしれません。サイダー自体がまだ黎明期であることや、及川さんの前職、コロナ禍という状況も合わさっているのだと思います。
人と人が繋がる
楽しくて幸せな空間を作る

S : これからサイダーを知る人に向けて、手軽に飲める国産のサイダーでお薦めはありますか?
T : 好みによってすごく分かれると思いますが、『Son of the Smith Hard Cider』さんは外せないのではないでしょうか。ブランドとして確立していて、都内でイベントを行うと多くの人がつくり手に会いに行くぐらいファンがいます。限定販売ですが、『もりやま園』さんの「ドルゴ」も衝撃を受けました。岩手の 『紫波サイダリー』さんや、秋田『OK,ADAM』さんも大好きです。
S : ワイン好きな人にお薦めはありますか?
T : サイダーはワインから入ってくる人とクラフトビールから入ってくる人でお薦めするものが違うのですが、ワイン好きな人でしたら、福島の『ふくしま逢瀬ワイナリー』さんのシードルや長野の『カモシカシードル醸造所』さんもクオリティが高くて是非試していただきたいです。 哲学がしっかりして尊敬している、仙台の『秋保ワイナリー』さんや、長野の『VinVie』さんも深みや複雑さがあり人気があります。それぞれタイプが違うのでぜひ飲み比べてみて自分好みのものを見つけていただけたらと思います。
O : どのようなものを普段飲んでいるかで、本当に好き嫌いは分かれますよね。

T : 及川さんが目指す味はありますか?
O : 今、これに近づけたいというのが明確にあれば、僕がこれから造る意味はあまりないかなと思っています。でも、はっきりしていることはプロダクトが中心にはないということです。僕はやはりパブのような空間自体が好きなので、多くの人が集ってくれるような、お客さんが手に取りやすいものを造りたいと思っています。もちろん、僕の残りの人生をかけてハードサイダー造りに真剣に向き合っていくのですが、味をとことんまで追求するというよりも、空間やコミュニティをつくっていくことに重きを置いています。
S : おそらくその価値観は地域性に依っているのかもしれません。岩手県紫波町は人口3万人ほどのまちなのですが、地方特有の過疎化の問題があり、新しくまちをつくっていく過程にあります。だから、ブルワリーからまちがつくられていくようにまちづくりの一つとしてサイダリーがあるという意識が強い。そこに人が集うことがとても重要なことなのだと思います。
O : 僕は飲める場所、そこに集う人たちの気持ちを整えるのが仕事で、純粋に味を突き詰めていくというのは、次世代の造り手に担ってもらいたいと思っています。だからプロダクトを推していく、というよりもこのサイダーカルチャーの世界観をまずは広めていきたい。というのも、イギリスやアメリカといったそれぞれのバックボーンとなるカルチャーが行き過ぎると、どうしても排他的になってしまいますよね。そうすると広がるものも広がらないので多様性を僕たちは大切にしていきたいと思っています。
T : いいですね。その集約地に及川さんがいることになる。
O : 僕が造って僕が提供したハードサイダーが一番だとは思わないし、そうなりたいとも思いません。でも、飲んで楽しいと思える場所としては一番になりたい。
T : その媒介するものがハードサイダーだったんですね。

O : そうです。だから極端に言ってしまえば、ハードサイダーはツールであって、手段としてのハードサイダーなのだと思います。
S : 僕や及川さんがいるコミュニティの価値観は、楽しくて幸せな「空間をつくる」「場をつくる」ということをとても大切にしています。「Green Neighbors」という名前も、ハードサイダーを通じて良き隣人をつくるという意味なので、プロダクトを蔑ろにするつもりはありませんが、その先にある人と人の繋がりを意識したものになっています。
サイダーカルチャーにとって
無くてはならないオープンマインド

O :『Cidernaut』は今後どのような展開を考えていますか?
T : 僕は基本的に売り手で広める側でやっていくつもりですが、現在、『Son of the Smith Hard Cider』さんのタンクを一つ押さえてもらって、いろんなプレイヤーとコラボしていくプロジェクトを計画しています。
S : タンクをシェアするというのは、そこでコミュニティが生まれて繋がっていく感じがしていいですね。
T : 僕たちみたいな弱小は、有名なメーカーさんの名前を借りるというものもありますし、そもそも、その方が面白いと思っています。コラボをすることによって知ってくれる人や、サイダーファンが増えていったら嬉しい。もしかしたら、スタンプラリーのようなこともできるかもしれませんね。いずれにせよ、手堅く、楽しくやっていきたいと思っています。
S : 武田さんと及川さんの波長が会うのは、こうしたシェアリングを楽しむというオープンマインドがあるような気がしますね。
O : おそらく間口を広げたいとか、ハードサイダーを楽しむ人たちを増やしたい、という根本に流れている気持ちがそうさせているのかもしれません。
T : 確かにそうですね。表現こそ違えど、向かっている場所は一緒だと思います。
S : そこに向かうモチベーションは何なのでしょうか?
T : 何でしょうかね。でも0を1にしている感覚が、やりがいがあって楽しいということはあるかもしれません。もちろん、本当は楽をしたいのですが、何故か苦労する方に引き寄せられてしまう 笑。
S : チームは小さいけど、0から作っている時は、周りと一緒に作り上げている感覚があるじゃないですか。本気で人と人がぶつかり合いながら、成長できるのは楽しいですよね。

T : もちろん、最終的に成功すればですけど 笑。確かに今が一番楽しい時期かもしれません。及川さんはどうですか?
O : 楽しいですが、これだけ多くの人に協力してもらっていますから失敗できないプレッシャーはあります 笑。でも、これからハードサイダーに携わってずっと仕事をしていくなかで、オープンマインドでいるということは忘れたくありませんね。気がつかないうちに忘れてしまうこともありますから。
T : 確かにこのサイダーカルチャーにとって無くてはならないマインドですね。でも及川さんの気質だったら平気な気がします。
O : いざオープンしてなかなか思ったように広まらないということもあるかもしれないので、そうした苦しい壁にぶつかった時、果たしてオープンマインドでいられるのかなと。
T : まだ黎明期のサイダーですから固定概念に固まる余裕も無いので、結果、良くなる方向を目指して変わり続けていくしかないのだろうと思います。でも、及川さんの言う通り大きくなった時、頑固に「これが正解だ」と周りを断絶するようにはならないようにしなければと思いました。ありがとうございます。教訓にします 笑。






